着物に合わせる帯選びに迷ったりしませんか。
せっかく着物を着るならおしゃれに着こなしたいですよね。
帯には着物を引き立て、全体のバランスをとる重要な役割があります。
帯によって落ち着いた雰囲気や華やかさを出せたりと印象が変えられ、個性を出せるのがポイントです。
そこで今回では、帯の種類と着物の合わせ方を紹介します。
ぜひ最後までチェックして、お気に入りのコーディネートを見つけてくださいね。
帯の歴史を知ろう
帯は室町時代に将軍の足利義満が「平ぐけ帯」と呼ばれる、幅6cmの長さ3mあるひもを結んだことから始まりました。
安土桃山時代までは袴に細いひもを巻いていました。平ぐけ帯ができたことから、女性の衣服は次第に「小袖と帯」のスタイルに変わっていきます。
江戸時代中期、流行っていた歌舞伎に人気役者の上村吉弥(うえむらきちや)がいました。
上村吉弥が幅広い帯を結んで余ってしまう部分を垂れるようにしたことから、今のお太鼓がある帯の形ができ、今日まで受け継がれています。
帯は大きく分けて4種類
帯は大きく分けて丸帯、袋帯、名古屋帯、半幅帯の4種類があります。
帯には着物と同じく「格」があり、着るシーンに合わせて選ぶ必要があります。
以下では、帯の種類とそれぞれの特徴を紹介します。
丸帯
丸帯は幅70cmある1枚の帯地を2つ丸く折って仕立てられ、幅3cm長さ4m3cmになります。
丸帯は江戸時代から最も格式が高いものとされ、礼装用として着用されていました。
今では高価であまり出回らなくなりましたが、花嫁の引き振袖や白無垢、舞妓さんの衣装として使われています。
帯の両面に柄が入っていて、素材は絹の銀糸、金糸を多く使って織られた生地で重厚感があります。
古典文様や吉祥文様の柄が刺繍されている帯が多いです。
袋帯
袋帯は柄がある表地と柄がない裏地の異なる2枚の帯地を袋状に縫い合わせて仕立てられ、幅31cmさ4m30〜5cmあります。
袋帯は丸帯の次に格が高く、結婚式や成人式などで着る留袖や振袖、訪問着などフォーマルなシーンの着物に合わせるのが多いです。
裏地を無地にしたことで丸帯より軽量化し、今では礼装用として最も多く着られています。
さらに柄や紬の素材を使ったものは付け下げや色無地などカジュアルな場面にも着用できます。
名古屋帯
名古屋帯は大正時代に丸帯や袋帯だと時間がかかってしまうため作られた、胴回りの部分が半幅で幅30cm長さ3m60cmの帯です。食事会や演劇鑑賞などのカジュアルなシーンから結婚式や同窓会などのセミフォーマルな場面まで幅広く使えます。名古屋帯は一重太鼓で重ならないという意味合いから、黒やグレーの名古屋帯は服喪のようなシーンに使われることもあります。
半幅帯
半幅帯は幅1cm長さ3m6cmで他の帯と比べて細いのが特徴で、全体に柄が織られていて裏表両方使えるものが多いです。
半幅帯には柄の違う2枚の生地を縫い合わせ作られた小袋帯と、1枚の生地で作られた薄く通気性がいい単衣帯があり、どちらも夏に使われます。
半幅帯は主にお出かけや普段着などカジュアルなシーンで着る小紬や小紋、浴衣に合わせます。
さらに締めや帯揚げ、帯枕などの小物なしで結べるので初めての人にも簡単です。
帯の柄付には3種類ある
帯には全通柄、六通柄、お太鼓柄の3種類の絵付けがあります。
中でも全通柄は最も高価で、帯全体に柄が織られていて華やかさと重厚感があります。
六通柄は帯の6割程に柄が入っていて、胴回りに巻く見えない1周目の部分は無地です。
お太鼓柄はとび柄やポイント柄とも言われていて、「タレ」と呼ばれるお太鼓の下から出てる先端など見える部分に柄が入っています。
一部に柄がある帯は体形に合わせて綺麗に出すように結ぶのが難しいとも言われています。
着物に合う帯の選び方ポイント
着物に合う帯の選び方にはポイントがあります。
例えば、シンプルな白やクリーム色の帯を使うと、どんな色や柄の着物にも合わせやすく上品な印象になります。
着物の柄に入っている色の帯を選ぶと、統一感のあるコーディネートで落ち着いた雰囲気になりおすすめです。
着物と反対色で濃淡なものを選ぶと着物と帯がそれぞれ際立ち、ワンランク上のコーディネートになります。
特に色無地など柄の少ない着物に反対色を合わせるとアクセントになります。
まとめ
この記事では、帯の種類や着物との合わせ方を紹介しました。
帯は着物と同じように「格」があり、着るシーンによってふさわしい選び方があります。
着物だけではなく、帯の選び方一つでも印象が変わるのでコーディネートの幅が広がります。
帯は約700年もの時を経て形が変化し、美しく魅せる現代の帯の形が作られました。
ぜひ、この記事を参考にして帯の知識を深め、自分にぴったりの帯と着物を見つけ個性を楽しんでみてくださいね。
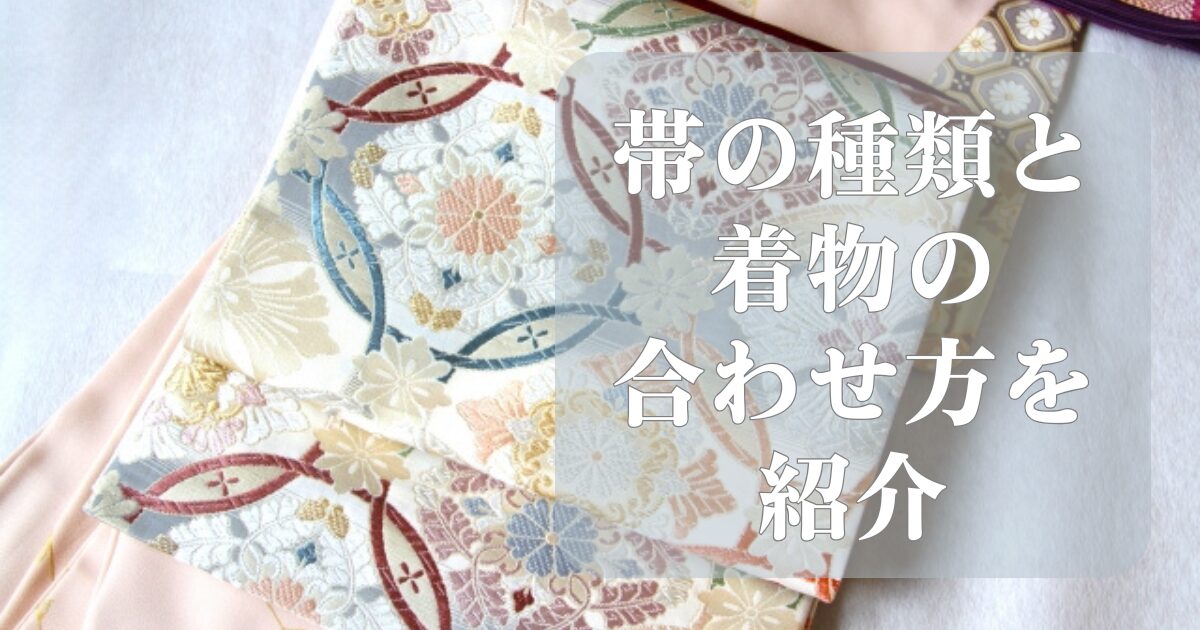
コメント