※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
四季の移ろいを大切にする日本の文化の中で、着物はまさに季節感を映す衣服です。
着物を長く美しく保つためには、衣替えのタイミングと適切な保管方法が欠かせません。
今回は、着物初心者からベテランまで役立つ「衣替えの時期」「メンテナンス方法」「保管のコツ」を徹底解説します。
着物の衣替え時期
着物には「薄物(うすもの)」「単衣(ひとえ)」「袷(あわせ)」という季節に応じた仕立てがあります。それぞれの特徴を理解しておくと、季節にふさわしいコーディネートが楽しめます。
薄物→単衣→袷の流れ
- 薄物(7〜8月)
透け感のある絽や紗(しゃ)、麻素材が中心。真夏に涼やかに見せるための装いです。 - 単衣(6月・9月)
裏地のない仕立て。梅雨時や残暑の季節に最適で、軽やかさと快適さを両立。 - 袷(10月〜5月)
裏地が付いた仕立て。秋から春までの主流で、フォーマルな場でも用いられます。
この流れを押さえることで、季節の変化を体感しながら着物を楽しむことができます。
地域別の衣替え目安
日本は南北に長いため、気候によって衣替えのタイミングは異なります。
- 北海道・東北地方:気温が低いため袷の時期が長く、単衣は短め。
- 関東・関西:暦通りに衣替えする人が多く、6月と9月は単衣が活躍。
- 九州・沖縄:暑さが長引くため、単衣や薄物を10月まで着ることも。
「暑ければ薄く、寒ければ厚く」という実用的な視点で選ぶことも、現代の着物生活には大切です。

衣替え前のメンテナンス
衣替えの際には、着物をただ入れ替えるだけではなく、状態チェックとケアが欠かせません。
陰干しと虫干し
着物を長期保管する前に、風通しの良い場所で陰干しを行い、湿気を取り除きます。特に梅雨明けや秋晴れの乾燥した日がおすすめ。
また、年に一度は「虫干し」をして、タンスや桐箱から取り出して湿気を飛ばすと、カビや虫食いの防止になります。
シミ・汚れチェック
- 衿や袖口のファンデーション汚れ
- 裾の泥はね
- 食べ物や飲み物のシミ
これらは放置すると時間とともに落ちにくくなります。気付いたら早めに専門の悉皆(しっかい)業者に相談するのが安心です。

着物保管のベスト方法
美しい着物を次の季節まで守るには、正しい保管方法が不可欠です。
たとう紙の使い方
たとう紙は、和紙に防湿・通気の効果があるため着物保管に最適です。
- 年に1度は新しいものに交換する
- 黄ばみやカビ臭があれば早めに取り替える
- 折り目に沿って丁寧に包む
桐箪笥や専用ケースに入れるとさらに安心です。
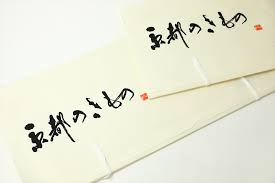
防虫剤の選び方
着物用の防虫剤は「無臭タイプ」がおすすめです。香りの強い防虫剤は着物に移り、次に着るときに不快感を与えることもあります。
- 防虫成分の種類を混ぜない(化学反応で効果が落ちる場合あり)
- 着物に直接触れないように配置
- 定期的に交換して効果を保つ

まとめ
着物の美しさを長く保つには、衣替えのタイミングを意識し、適切なメンテナンスと保管を行うことが欠かせません。
- 薄物・単衣・袷を季節に応じて切り替える
- 衣替え前に陰干し・シミチェックを徹底する
- たとう紙と防虫剤を正しく使って保管する
これらを実践すれば、大切な着物を次の世代まで受け継ぐことも可能です。ぜひ今日から実践して、季節ごとに心地よい着物ライフを楽しんでください。
- 【着物でお出かけ】3月千葉県編!歴史や和の景観をお気に入りの装いで楽しもう
- 日本舞踊の伝統衣装について解説!舞の表現を支える着物の特徴とは?
- 着物で音楽会を楽しむ着こなし完全ガイド!ジャンル別のコーディネートを解説
- 着物にまつわる人間国宝の魅力とは?代表的な人物と受け継がれている技術を紹介
- 2月に着物で楽しめる都内のスポットを紹介!梅まつりで季節の移ろいを味わおう

コメント